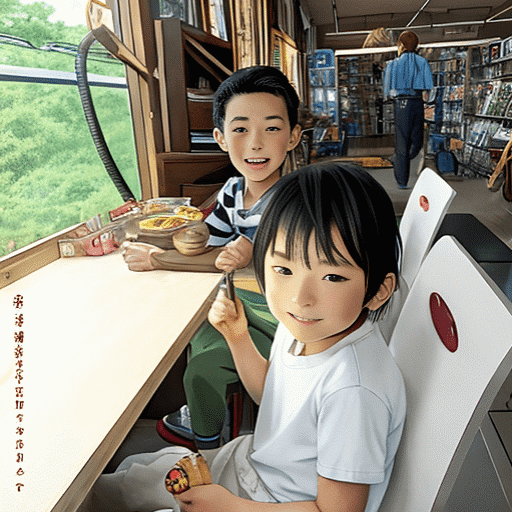さて、今日はジブリの宮崎駿を紐解く 「魔女の宅急便」編 黒猫のジジはなぜ喋れなくなったのか?という話題です。
僕も子どもの頃から大好きだったスタジオジブリの宮崎駿監督なんですが、やはり巨匠といいますか、子どもの時はただひたすらにカッコ良くて、面白いと感じていた作品の数々も、いま改めて大人として作品を見直したり、いろいろな考察系の動画を見てみたりすると、また新たな発見や、解釈のちがいにハッとすることや、なるほど、あのシーンはこういう捉え方をするとこういう解釈も成り立つのか、と作品の謎や伏線の多面的な構造を捉えることができたりして、ああ、やっぱり宮崎駿監督はスゴい人だなあ、なんて思ったりもします。
宮崎駿監督の作品というのは、ジブリの初期のころなんかは割と理詰めといいますか、ストーリーの設定や起承転結なんかがわりとハッキリしていて、それがだんだんと、「ハウルの動く城」や「千と千尋の神隠し」辺りから、なんだか抽象的で伏線や謎なんかもキチンと回収しないまま、すごい勢いみたいなもので完結していく形式に変わっていったように感じるのですが、僕はやっぱり子どもの頃に観た「天空の城ラピュタ」や「魔女の宅急便」なんかが強烈に印象に残っていて、今でも大好きな作品です。
今日はそんな「魔女の宅急便」の謎や伏線の回収なんかをすこし紐解いていこうと思います。
なお、これらは、僕がいろいろな考察系の動画や、作品を調べていくなかで見聞きしたお話なんかを、僕なりの解釈で説明していくので、その辺りは悪しからずご了承ください。
まず、魔女の宅急便の成り立ちとして、宮崎駿監督の作品以前に、原作者として角野栄子さんが書いた児童文学がありまして、その原作をもとに宮崎駿監督がイメージボードを作成、頭に大きな赤いリボンをつけた少女、キキが出来上がったそうです。
宮崎駿監督曰く、思春期の女の子というのは、こういった邪魔になるくらい象徴的な赤いリボンのような自意識をもって、毎日を送っているようなものだから、この娘をオレは主役に据えた物語を描く、と仰っていたらしく、そこから映画作りがスタートしたそうです。
また、そんな自意識過剰な女の子、キキがどうにか13歳で、見知らぬ街で一人で生活しようと奮闘してストーリーは進んでいくのですが、お話の途中、魔法のホウキが弱くなって飛べなくなってしまったり、今までお喋りができていた黒猫のジジと会話ができなくなってしまうシーンがあるんですが、どうもこの場面は、ストーリー的に同時進行で訪れるので、ごっちゃにしがちなんですが、理由はそれぞれ別にあるようで、魔力が弱くなったのは一時的な胎動のようなもので、後に大きく覚醒する前触れとして弱くなっていただけらしく、確かにその後キキは自身の力を大きく覚醒させ、デッキブラシをホウキ替わりに、以前よりパワフルに、またスピードもより速く使いこなせるようになっていて、蛹から蝶のような、一皮むけた成長を見せてくれているシーンだったようですね。
あとは、黒猫のジジの喋れなくなった理由は、どうもジジは初めから喋れない存在だったらしく、作中で話していたのはキキの幻想、つまりはイマジナリーフレンド、心の中のお友達だったということで、キキは自分の中のもう一人の自分と喋っていたに過ぎず、作中ではキキが自分の中の嫌な自分を意識することによって、イマジナリーフレンドとしての役割を終えて、ただの普通の黒猫に戻ったに過ぎないようです。
まあ、僕なんかの解説よりも、実際は映画の作品に触れて、感じることは人それぞれで、解釈は違って良いものだと思いますし、そんな捉え方もあるのかな、程度に感じていただけたら幸いです。
以上、ジブリの宮崎駿を紐解く 「魔女の宅急便」編 黒猫のジジはなぜ喋れなくなったのか?という話題でした。