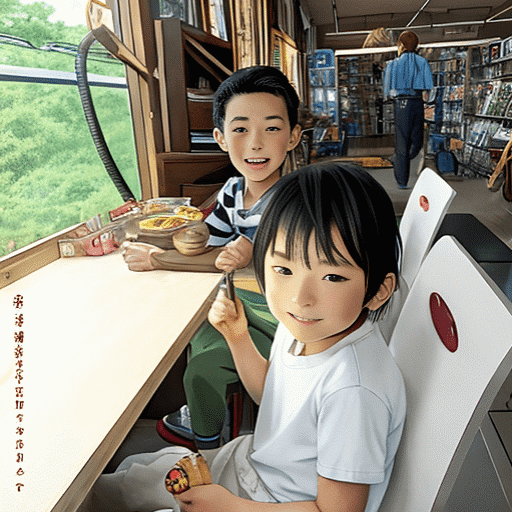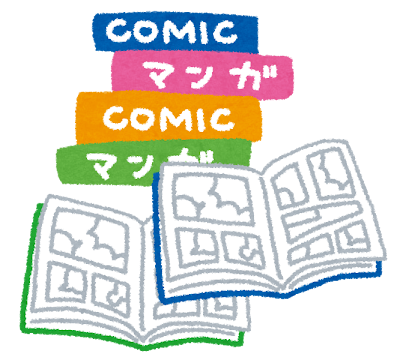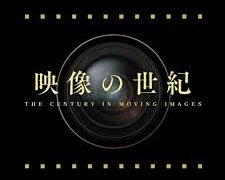さて、今日は日本の漫画、ゲーム文化って、やっぱり退屈で窮屈な現実社会の緩衝材の役割として重要だよねという話題です。
まあ、僕自身、子どもの頃から漫画やゲームがかなり好きな方で、小さい頃から月間コロコロコミックや週刊少年ジャンプは毎週欠かさず読んでいましたし、あの頃は今よりエンタメの種類も限られたもので、子どもが気軽に室内で楽しめるものと言えば、だいたいテレビか漫画、児童文学、あとはテレビゲームくらいだったでしょうかね。
あとは、やっぱり身体を動かすのが好きな子はだいたい外で野球やサッカーなんかのスポーツが定番だったような気がします。
僕の場合は、球技ものは全然才能がなかったので、スポーツ全般はほとんど取り組まず、小学校の頃は、ガチャポンのキン肉マン消しゴムというフィギア集めや、ビックリマンシールなんかのコレクション集めに必死になっていたりして、今思えば、なぜあんなに楽しく夢中になれていたのか不思議なくらいです。
きっと、子ども心にキン肉マンの熱い戦いのストーリーや、ビックリマンの不可思議な世界観が楽しくて、その魅力に引き込まれていたんだと思います。
そう、そして中学校や高校生なんかになってくると、学業や将来に関する現実問題や、目の前に差し迫ってくる課題やテストなんかが重くのしかかってきたりして、そういう窮屈な現実社会の気晴らしやガス抜きとして、漫画やゲームはうまく活用してきたような気がするんですよね。
まあ、言い方を変えると逃避行動なのかも知れませんが、気分を変えたいときや、疲れたときは甘いものを食べたくなるように、口当たりがよく、スッと自分のなかに消化、吸収できて楽しいひと時を与えてくれる漫画やゲームは、本当に自分にとってありがたい存在でした。
自分自身、中学生のときに読んだ、浦沢直樹さんの「マスターキートン」という作品で、世界史に興味を持つきっかけを与えてもらったり、京都アニメーションが作ったアニメで、「CLANNADクラナド」という作品で、好きな人と結婚して家族を持つことの意味や大切さを教えてもらったり、少なからず影響を与えられた作品もたくさんあったりします。
あと、好きなゲームクリエイターとして、小島秀夫監督の作る作品はどれもストーリーも考えさせられるものが多く、ゲーム性も秀逸で大好きだったりしますね。
世の中には漫画やアニメ、ゲームの楽しさは一過性のもので、それは現実にはなんの付加価値も与えてくれない、なんて意見も存在すると思いますが、少なくとも僕の場合、自分の好きな作品はいまの自分の血肉となって、ちゃんと実を結んでくれているような気がするんですよね。
それに、たとえ一過性のものであれ、楽しい時間を過ごさせてくれたのは間違いのないことで、それはこの窮屈な社会で癒しの効果を持つ、とても素晴らしいことなんだと思います。
以上、日本の漫画、ゲーム文化って、やっぱり退屈で窮屈な現実社会の緩衝材の役割として重要だよねという話題でした。